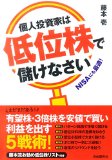拙著「個人投資家は低位株で儲けなさい」が発売されました。
株価が安い「低位株」に投資する方法を解説しています。
自由国民社刊で、定価1,512円(消費税込み)です。
福知山線と伊丹
先日の福知山線の事故では、お亡くなりになられた方の捜索が終わり、これからは原因究明が本格化する段階になりました。
原因究明には時間がかかると思いますが、二度とこのような事故が起こらないように、しっかりと原因を究明していただきたいものです。
ところで、私は伊丹の生まれで、26歳まで伊丹で過ごしました。今は36歳なので、10年ほど前までは伊丹にいたことになります。
私が子供の頃は、福知山線は単線非電化のローカル線でした。普通列車は1時間に1~2本程度の運行で、ディーゼル車や客車の列車が走っていました。
客車にいたっては、昔は乗降口を手動で開けるような旧式のものが走っていました。いつだったか、伊丹駅で客車から降りるときに、完全に停車する前に飛び降りて、ホームで転んだことを覚えています。
そんなローカル線だったので、大阪方面へ行く際には福知山線を使うことはまずなく、私鉄の阪急電車を使っていました。
福知山線が全線電化されたのは、1986年のことでした。
それによって、宝塚の北にある三田や篠山といった地域が大阪の通勤圏に入り、福知山線はローカル線から脱皮し始めました。
1995年に阪神大震災が起こりましたが、これも福知山線の躍進に一役買ったと言えます。
阪神大震災の時には、阪急電車の伊丹駅が倒壊して、仮駅での営業が3年ほど続き、不便な状態でした。
それによって伊丹の人の流れが変わり、福知山線の利用者が増えるきっかけになったと思います。
ちなみに、阪神大震災までは阪急伊丹駅の周りに商業施設が集まっていましたが、震災後には阪急伊丹駅前にあったジャスコが閉店し、一方ではJR伊丹駅のそばにダイヤモンドシティという大型商業施設がオープンしています。
また、伊丹の市営バスもかつては阪急伊丹駅から放射状に路線が延びていましたが、今ではJR伊丹駅が始発の路線も増えています。
そして、1997年に東西線が開業し、福知山線と東海道線や学研都市線との連絡が格段に良くなって、さらに利便性が上昇しました。
ちなみに、先日のエントリーで書いたとおり、ついこの前に実家へ帰省する際に福知山線に乗ったばかりです。
新大阪で新幹線から乗り換えて、伊丹までスムーズに行けるようになったので、福知山線に乗ることが多くなったわけです。
1986年の電化からわずか10年ほどで、福知山線はローカル線から劇的に進化したことになります。
関西のJR線の中で、もっとも発展した路線だと言えるでしょう。
これだけの進化を遂げたにもかかわらず、旧式のATSが使われて続けていたということは、今回の事件の原因の1つでしょう。
また、尼崎駅では乗り換え時間を最短にするために複雑なダイヤが組まれています。それを考えても、最新の設備を導入しておくべきだったのではないでしょうか。
・・・とここまで書いて、テレビのニュースを見たところ、「伊丹駅でのオーバーランは、実は40メートルではなく、60メートル程度あったのではないか」という話が出てきました。
JRの会見を見ていると、責任逃れをしようとしたり、話が二転三転したりしていますが、いい加減にしろと言いたいです。